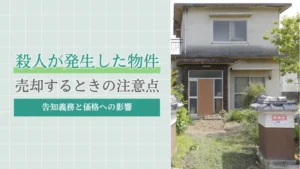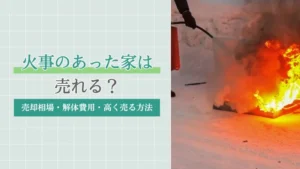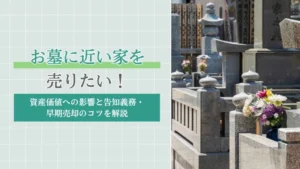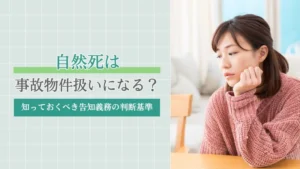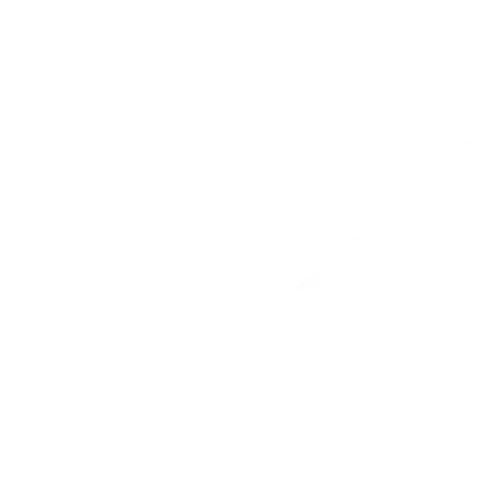2021年10月、事故物件をどこまで告知すべきかのルールをまとめた「人の死の告知に関するガイドライン」が作られました。
これまで入居希望者にどこまで話すべきかという基準は曖昧でしたが、新ルールの登場によって判断基準が明確になり、より安心して不動産取引ができる環境が整いつつあります。
この記事では、ガイドラインの重要なポイントや、知っておくべき実際の対応方法について解説します。
- 2021年ガイドラインで決まった告知基準
- 事故物件として告知すべき期間・範囲
- 最新の告知義務ルール
事故物件のガイドラインが制定された理由
2021年10月に本ガイドラインが策定されるまで、事故物件の告知義務には明確な基準が存在しませんでした。
そのため、何が告知対象で、いつまで伝えるべきかという判断は各不動産会社の裁量に委ねられていたのが実情です。
基準が曖昧なことで不動産取引において以下の2つの問題がありました。
- 契約トラブルと損害賠償リスク
告知の範囲が不明確なため、慎重になりすぎて過剰な情報を伝えてしまい成約を逃すケースや、逆に告知不足によって契約後に損害賠償請求へと発展するトラブルが頻発。
- 高齢者の入居拒否問題
「室内で亡くなれば、理由を問わず事故物件になる」という誤解から、孤独死を恐れるオーナーが高齢者の入居を敬遠する動きの広がり。
このような事態を受け、「自然死」と「告知が必要な事案」を適切に区別し、公平な取引環境を整えること。
そして、高齢者が安心して住まいを借りられる社会を実現することを目的に、新たなルールが明文化されたのです。
事故物件のガイドラインの枠組み
ガイドラインは居住用不動産の取引において、宅地建物取引業者が負うべき調査義務と告知義務の解釈を示したものです。
対象となるのは居住用不動産のみで、オフィスや店舗などの事業用不動産は含まれていません。
基本的な考え方は、買主や借主が契約を締結するかどうかの判断に影響を及ぼす可能性がある事案について適切に告知を行うというものです。
人の死が発生したからといって、すべてのケースで告知義務が生じるわけではなく、死亡の状況や原因、社会的影響などを総合的に判断して、告知の必要性を決定します。
宅地建物取引業者が売主や貸主に対して告知書などへの記載を求めることで、調査義務を果たしたとみなされます。
物件の近隣住民への聞き込みや、インターネット上の情報収集までは求められていません。
売主や貸主が故意に事実を隠蔽すれば、損害賠償を請求される可能性があります。
告知が必要な場合と不要な場合の具体的な基準を示すこと、賃貸契約と売買契約で異なる告知期間を設けられたことによって不動産業界全体で統一的な対応が可能になり、取引の透明性が向上しています。
告知義務が必要なケース
告知義務が発生するのは、買主や借主の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる人の死が発生した場合です。
具体的には三つのケースに分けて考える必要があります。
自殺・他殺・事故死の場合
自殺、他殺、事故による死亡があった物件は、告知義務の対象となります。
この3つの死因があったという事実は、心理的な抵抗感が強いと考えられるためです。
もし死因が不明な場合であっても、取引に影響を及ぼすと判断される場合は告知が必要になります。
賃貸契約の場合、室内で自殺や他殺が発生した場合は概ね3年間の告知義務が生じます。
売買契約の場合は取引金額や買主が被る損害が大きいため、期間制限がなく何年経過していても告知が必要です。
| 取引種別 | 告知が必要な期間 |
| 賃貸契約 | 事案発生から概ね3年間 |
| 売買契約 | 期限の定めなし |
集合住宅の場合、該当する住戸内で発生した事案については、その住戸に入居する人に対してのみ告知義務が生じます。
隣の部屋や上下階の住戸に対しては、原則として告知義務はありません。
ただし、共用部分で発生した場合は別の扱いになります。
特殊清掃が行われた場合
自然死であっても長期間放置されて特殊清掃が必要になれば、心理的瑕疵が発生したとみなされます。
遺体の発見が遅れて腐敗が進み、臭気や汚染が発生した場合がこれに該当します。
特殊清掃とは、壁や床の張り替え、配管の洗浄、消臭処理など通常の清掃では対処できない汚染や臭気を専門的な技術で除去する作業のことです。
孤独死の場合、発見が早ければ特殊清掃が不要なケースもありますが、その場合は自然死として扱われ、原則として告知義務は発生しません。
発見までの期間と物件の状態が、告知義務の判断基準となります。
社会的影響が大きい事件の場合
事件性や周知性、社会に与えた影響が特に大きい事案については、物件の価値や住み心地に深刻な影響を与えるとみなされ、告知の必要性が生じます。
全国ニュースで大きく報道された事件や、メディアで繰り返し取り上げられた事案、あるいは地域社会に強い衝撃を与えた事件などがこれに該当します。
連続殺人事件のような凄惨な事案が発生した物件は、周囲の住民の記憶に強く残っていることが多く、入居後に第三者から事実を知らされる可能性が高いためです。
社会的影響の大きさは、報道の規模、事件の内容、地域での周知度などを総合的に判断して決定されます。

告知義務が不要なケース
ガイドラインでは、告知義務が不要なケースも示されています。
自然死や日常生活での不慮の死
老衰や持病による病死といった「自然死」については、原則として告知義務はありません。
人が居住する場所において自然死が発生することは十分に予想される事態であり、それを一律に告知対象とすることは、不動産取引の安定性を損なうだけでなく、遺族やオーナーへの不当な不利益につながると判断されているためです。
また、自宅内での転倒事故や入浴中の溺死、食事中の誤嚥(ごえん)など、日常生活の中で起きた「不慮の事故による死」も、同様に告知は不要とされています。
ただし、自然死や不慮の事故であっても発見が遅れたことで遺体の腐敗が進み、特殊清掃やリフォームが必要になった場合は、前述したとおり告知義務が発生します。
隣接住戸や共用部分での死
集合住宅において隣の部屋や上下階の住戸で人の死が発生した場合、その事実を他の住戸の入居者に告知する義務は原則としてありません。
事故が発生した住戸に直接入居する人以外には、心理的瑕疵の影響は及ばないと考えられているからです。
また、通常使用しない共用部分での死亡についても、告知義務は発生しません。
例えば、屋上や機械室、管理人室など、入居者が日常的に使わない場所は入居者の生活空間とは切り離されているため、心理的な影響は限定的だと判断されています。
賃貸契約と売買契約の告知義務の違い
ガイドラインでは、賃貸契約と売買契約で告知義務の期間が区別されています。
賃貸契約における告知義務期間
賃貸契約における告知義務の期間は、ガイドラインにおいて「概ね3年」と定められています。
自殺や他殺、事故死が発生してからこの期間が経過すれば原則として告知義務は消滅します。
この3年という数字は、過去の裁判例において賃料などの取引条件に影響を及ぼす期間として認められてきた年数に基づき、目安として設定されたものです。
期間を計算する際に注意が必要なのは、起算点が発生時ではなく「発覚時」とされる点です。
遺体の発見が遅れたケースでは、実際の死亡時期と発覚時期に差が生じることがありますが、あくまで事実が明らかになった時を基準とします。
特殊清掃が行われた場合、清掃が完了し、客観的に事案の影響が除去された時期が起算点となります。
ただし、3年が経過すればいかなる場合も告知が不要になるわけではありません。
事件性や周知性が極めて高い事案、例えば全国ニュースで大々的に報じられたり、地域社会で長く語り継がれたりしているようなケースについては、社会的な影響の大きさを考慮し、3年を超えても告知が求められることがあります。
今回のガイドライン制定によって、かつて不動産業界の一部で行われていた「事故後に一度でも誰かが入居すれば告知義務がなくなる」という慣行は否定されました。
以前は、入居者が一人入れ替わることで告知義務が消滅すると解釈する向きもありましたが、現在では、後続の入居者が誰であるかに関わらず、事案の発覚から3年間は告知義務が継続するというルールが徹底されています。
売買契約における告知義務期間
売買契約の場合、告知義務に期間制限はありません。
何年経過していても、自殺や他殺、事故死があった事実は買主に伝えなければなりません。
この違いは、取引金額の大きさと、買主が被る損害の重大性から生じています。
不動産の売買は多額の資金が動く取引であり、購入後に事実を知った場合の経済的損失は計り知れません。
賃貸契約であれば契約を解除して別の物件に移ることも比較的容易ですが、購入した不動産を手放すことは大きな負担となります。
ただし、自然死や日常生活での不慮の死については、売買契約においても告知義務はありません。
告知内容について
実際に告知義務を履行する際には、何をどこまで伝えるべきかという実務上の判断が重要です。
ガイドラインでは、告知すべき基本的な内容として「発生時期」「場所」「死因」の三つが示されています。
- 発生時期:死亡した正確な日時が不明な場合、遺体が発見された「発覚時期」を伝えます。
- 場所;物件内のどの部屋や箇所で事案が生じたかを明示
- 死因:自殺、他殺、事故死といった区分を伝えます。
亡くなった方の氏名や具体的な状況など、プライバシーに関わる情報まで開示する必要はありません。
特殊清掃が実施された場合には、その事実も告知内容に含める必要があります。
物件の状態が事案によってどの程度の影響を受け、それに対してどのような清掃や消臭措置が講じられたかは、買主や借主が契約を判断する上での重要な指標となるためです。
また、事案に伴って大規模なリフォームや設備の交換が行われた場合も同様に、その内容をあわせて伝えることが望ましいとされています。
告知の方法については、後々の「言った・言わない」のトラブルを避けるため、口頭だけでなく必ず書面で行うべきとされています。
不動産会社(宅地建物取引業者)は、重要事項説明の際に口頭で丁寧に説明を行うとともに、その内容を書面に記載して買主や借主に交付します。
また、売主や貸主は、不動産会社に提出する「告知書」や「物件状況報告書」に正確な情報を記載し、事実を隠蔽していないという証拠を残しておくことが自身の身を守ることにも繋がります。
告知義務違反のリスク
告知義務を怠った場合、不動産取引においては極めて深刻な法的リスクを背負うことになります。
買主や借主から契約の解除を突きつけられるだけでなく、高額な損害賠償請求を受ける可能性まであります。
万が一、契約解除が認められれば、売主や貸主は受領済みの売買代金や賃料を返還する義務を負うだけでなく、相手方が被った実損についても賠償を求められます。
これには引っ越し費用や新たな物件の取得費用、さらには精神的苦痛に対する慰謝料までもが損害として認められる可能性があり、経済的な打撃は計り知れません。
また、この責任は物件の所有者だけにとどまらず、媒介する不動産会社にも重くのしかかります。
宅地建物取引業者は、売主や貸主から得た情報を適切に調査し、買主や借主へ伝える義務を負っており、このプロセスを軽視すれば業務停止などの厳しい行政処分を受ける対象となります。
一度こうした処分を受ければ、不動産会社としての社会的信用は大きく失墜し、その後の事業継続に深刻な影響を及ぼすことでしょう。
もし事実を把握していながら故意に隠蔽した場合には、単なる過失による告知漏れとは比較にならないほど重い責任を問われることになります。
意図的な情報の秘匿は、不動産取引の根幹である「信頼関係」を根本から破壊する悪質な行為とみなされるためです。
このようなケースでは損害賠償額もより高額に設定されやすく、裁判においても極めて厳しい評価を下されることになります。
まとめ
2021年10月に策定された「人の死の告知に関するガイドライン」により、それまで不透明だった事故物件の告知義務がはっきりしました。
賃貸契約では「概ね3年」の告知期間、売買契約では「期間制限なし」という基本的な枠組みが示されるとともに、老衰などの自然死は原則として告知不要、自殺や他殺は告知が必要といったルールが組み込まれています。
特筆すべきは、賃貸において長年慣習化していた「一人入居者を挟めば告知義務がなくなる」という曖昧なルールが、このガイドラインによって完全に否定された点です。
もしあなたが事故物件の売却や賃貸を検討されているのであれば、目先の成約にとらわれず、ガイドラインに沿って履行しましょう。