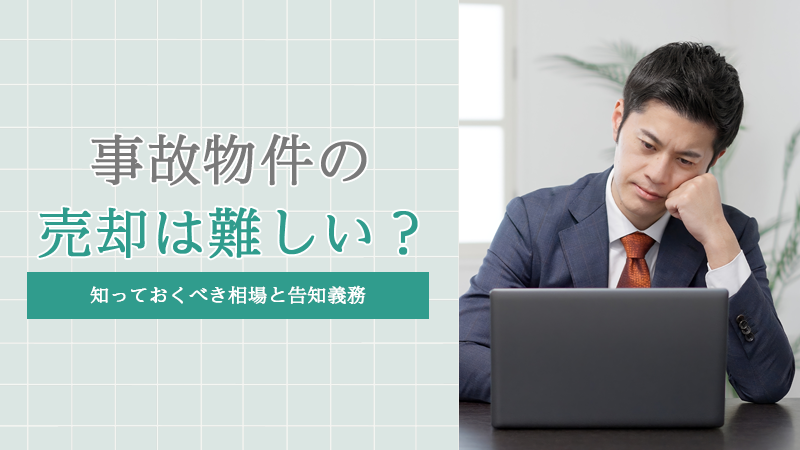
事故物件の売却を考える際「本当に売れるのか」「どの程度値下がりするのか」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
事故物件は、一般の物件に比べて買い手がつきにくく、売却までに時間がかかるうえ、市場価格も2〜5割ほど下がるのが一般的です。また「告知義務」もあるため、適切な対応を怠ると、契約解除や損害賠償請求のリスクもあります。
この記事では、事故物件の売却相場を事例別に解説しています。また、告知義務のポイントや売却成功のための手法についても紹介しているため「安全に売却を進めたい」「なるべく早く物件を手放したい」という方はぜひ一読ください。
事故物件を売却する際の基礎知識
事故物件をスムーズに売却するには、事故物件への理解を深めることが大切です。ここでは、事故物件の基本的な定義や特徴について分かりやすく解説します。
事故物件とは?
事故物件とは、住んでいた人が亡くなったことで「住みたくない」「購入したくない」と心理的な抵抗を感じる物件のことです。ただし、心理的な抵抗の感じ方は、人それぞれ異なるため、明確な基準はありません。
つまり、人が亡くなったからといってすべての物件が事故物件になるわけではなく、一般的に、自殺や他殺などがあった物件や長期間遺体が放置された孤独死は、事故物件に該当するとされています。
一方で、病気や老衰による自然死は事故物件にはなりません。しかし、発見が遅れたことで室内に強い臭いや汚れが残る場合は、買主の心理的な影響を考慮し、事故物件として扱うのが一般的です。
こちらの記事では、事故物件について解説しています。保有している場合の対処法も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
瑕疵物件の種類
瑕疵物件の瑕疵とは欠陥のことで、何らかの問題を抱えていることから、購入することで買主の心理的・金銭的負担となりやすい物件のことです。
そのため、一般の物件と比べて価値が下がりやすいのが特徴です。瑕疵には、大きく分けて、心理的瑕疵・物理的瑕疵・法的瑕疵・環境的瑕疵の4種類があります。以下で、詳しく解説します。
心理的瑕疵
心理的瑕疵とは不安や抵抗感があり、安心して暮らせない状態のことです。心理的瑕疵のある物件は「気味が悪い」「住みたくない」と思われやすく、一般の物件と比べて敬遠される傾向があります。
心理的瑕疵に該当するケースとしては、以下のものがあります。
・事故物件(自殺や他殺、長期間放置された孤独死があった物件)
・一般的な人が不安や嫌悪感を抱く可能性のある施設が近い物件(暴力団の事務所や葬儀場、火葬場などが近くにある)
とくに、事故物件は通常の生活では遭遇しない出来事が起こったという背景にあるため、抵抗感をもつ人が多いのが特徴です。
ただし、心理的瑕疵は、住む人の価値観によって受け止め方が異なります。気にならない人もいれば、絶対に避けたいと考える人もいるため、瑕疵の程度には個人差があります。
こちらの記事では、心理的瑕疵物件とはどういった定義があるのか解説しています。保有するリスクや売却方法も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
物理的瑕疵
物理的瑕疵とは、建物や土地に欠陥や損傷があり、安全性や快適性をそこなった状態のことです。物理的瑕疵があると、健康被害のリスクや、大規模な修理や解体が必要になる可能性があるため、物件の価値が下がることが一般的です。
物理的瑕疵には、建物に関する問題と土地に関する問題の2種類があります。建物に関する物理的瑕疵は以下の例です。
・屋根や壁の雨漏り
・シロアリ被害
・壁や基礎のひび割れ
・水道管や排水管の故障
・木材の腐食
・屋根や外壁にアスベストが含まれている
・耐震性能が低い
土地に関する物理的瑕疵は以下の例です。
・地盤が弱く、液状化や沈下の危険がある
・土壌が汚染されており、健康に悪影響をおよぼす可能性がある
物理的瑕疵は、本来あるべきでない欠陥や損傷を指すため、経年劣化による自然な摩耗や傷は含まれません。日常的な使用で避けられない劣化は、瑕疵とはみなされないのが一般的です。
法律的瑕疵
法律的瑕疵とは、建物や土地が法律のルールに違反している状態のことです。法律的瑕疵に該当する物件は再建築ができない、補強工事や建て替えが必要になる、売れにくいといったデメリットがあります。
法律的瑕疵には、主に建築基準法違反、都市計画法違反、消防法違反の3種類があります。建築基準法違反は以下の例です。
・建ぺい率・容積率・高さ制限の超過(建物の大きさに関するルール違反)
・耐火性能や耐震基準を満たしていない(安全性が法律の基準を満たしていない)
・接道義務違反(敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していないと建て直しができない)
都市計画法違反は以下の例です。
・市街化調整区域にある建物(市街化調整区域は無秩序な開発を防ぐためのエリアで、基本的に新たな建築が制限されている)
消防法違反は以下の例です。
・消火器やスプリンクラーが不足している
・防火扉がない
・避難経路が確保されていない
消防法違反は、とくにビルやアパートを1棟買いしたケースでは注意が必要です。
環境的瑕疵
環境的瑕疵とは、建物や土地自体には問題がなくても、周辺環境の影響で住みにくくなる状態のことです。具体的には、以下のようなケースが該当します。
・近隣に高層マンションが建ち、日当たりや風通し、眺望が悪化した。
・ゴミ処理場や工場が近く、窓を開けると悪臭が入ってくる。
・線路や高速道路の近くで、騒音や振動がひどい。
・飛行機の航路下にあり、エンジン音が常に響く。
環境的瑕疵は建物そのものの欠陥ではなく、周辺環境による問題です。そのため、心理的瑕疵と同じく、人によって感じ方が異なります。
たとえば、騒音や臭いを気にしない人もいれば、住めないと感じる人もいるため、明確な基準がありません。一般の人にとって問題がないか、住みづらくないかを判断していくことになります。
事故物件の売却相場
事故物件は、通常の不動産に比べて市場価格が下がりやすいため「どの程度値下がりするのか不安」と感じている方も多いでしょう。事故物件の売却相場は一律ではなく、亡くなった方の死因や発見状況によって異なります。
一般的に、心理的な抵抗が大きいものほど値下がり幅が大きくなり、抵抗が少ないものほど価格を抑えやすい傾向にあります。以下では、具体的な事例ごとの相場価格について解説します。
孤独死や病死があった事故物件
孤独死や病死があった物件は、一般的な市場価格よりも1〜2割程度相場が下がる傾向にあります。事故物件として扱われるものの、下落幅は比較的穏やかなのが特徴です。
孤独死や病死があった物件は、事件性がなく不慮の死に分類される傾向があり、買い手の心理的な抵抗が比較的小さいためです。大きく価値が下がることは少なく、適切な対応をすればスムーズな売却もできます。
ただし、発見が遅れた場合は注意が必要です。室内に強い臭いや汚れが残ってしまうと、買い手に避けられる傾向があるため、価格がさらに下がる可能性があります。特殊清掃やリフォームなどで汚れや悪臭を取り除くことが大切です。
こちらの記事では、孤独死と事故物件の関係について解説しています。売却価格への影響や注意点も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
自殺があった物件
程度安くなる傾向があります。不慮の事故とは異なり、自殺は買い手が不安や嫌悪感を抱く原因となりえるため、価格の下落幅が大きくなりやすいのが特徴です。
また、売却価格は、自殺の原因や室内の汚染範囲によって変動します。血痕や汚損がほとんど残らない自殺の場合、比較的減額割合が少なくなります。
こちらの記事では、自殺物件の買取相場について解説しています。高額で売却するコツや業者選びのポイントも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
他殺があった物件
他殺があった物件は、市場価格より3〜5割程度安くなる傾向があり、事故物件のなかでも売却が難しいとされています。他殺は「社会に与える影響が大きい死因」のため、心理的瑕疵の程度が非常に強いからです。買い手がつきにくく、大幅な値引きをしないと売却は困難といえます。
また、事件の認知度によっても売却価格は変わります。全国ニュースで報道された事件の場合、一般に広く知られているため、買い手の心理的抵抗がとくに強く、価格の大幅な下落は避けられません。事件の印象が長く残るため、不動産会社によっては買い取りを断られるケースもあります。
一方で、とくに報道はされていない事件の場合、物件の評価への影響は比較的小さくなります。しかし、売却時には告知義務があるため、一定の価格下落が想定されます。
こちらの記事では、事故物件の査定方法について解説しています。影響する要因や業者に依頼する流れも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
事故物件を売却する際の告知義務
事故物件を売却する際に気になるのが、告知義務です。告知義務違反となってしまうと、後々トラブルになりかねないため、必ず守らなければなりません。以下で、事故物件の告知義務の特徴を紹介します。
告知義務とは?
買主が事故物件を知らずに契約してしまうと「そんな出来事があったと知っていたら契約しなかった」と後悔する人が出てきてしまいます。こうしたトラブルを防ぐために、売主には事実を正直に伝える責任(告知義務)があります。
取り引きが成立する前に、事故物件であることを買主に伝えなければなりません。万が一、事実を隠して契約すると、後から契約解除や損害賠償請求を求められる可能性があるため注意が必要です。
ただし、人が亡くなったからといって、必ず告知義務が必要なわけではありません。一定のケースでは告知が不要とされており、告知義務の有無は判例や取引事例をもとに判断されます。
また、買主から直接質問された場合は、告知義務がない場合でも誠実に答えることが望ましいとされています。事故物件の売却を検討しているなら、事前に不動産会社へ相談するのが安全な方法といえるでしょう。
告知義務の期間
自殺や他殺などが発生した物件について、いつまでその事実を借主に伝える必要があるのかが問題となります。事故物件の告知義務の期間は、賃貸と売買で異なる基準が設けられています。
賃貸の場合は、国土交通省のガイドラインにより、事件発生から3年間は告知義務があるとされています。この3年間は、入居者が何度変わっても告知義務が継続するため、新しい借主にも必ず伝えなければなりません。
一方で、売買では現時点で明確な期間制限はなく、基本的に期間の定めなく告知義務が発生すると考えられています。
売買は賃貸と比べて取引金額が大きく、万が一購入後に「住めない」となった場合、買主への影響が大きいためです。つまり、事故物件を売却する際は、事件から何年経過しても、必ず買主に伝える必要があります。
※出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001427709.pdf)
こちらの記事では、事故物件の告知義務について解説しています。違反した際のリスクも取り上げていため、ぜひあわせてご覧ください。
事故物件を売却するコツ
事故物件は、買主が心理的な抵抗を感じやすいため、通常の不動産よりも売却に時間がかかり、相場も安くなる傾向があります。
しかし、適切な対策をとることで、スムーズに価格の下落を抑えて売却することも可能です。以下で、事故物件をできるだけ早く、高く売却するための方法を紹介します。
リフォームをする
事故物件のなかには、価格の安さを理由に購入を検討する人もいます。一般的に、事故物件は市場価格の1〜5割ほど安く販売されるため、心理的瑕疵を気にしない買い手にとってはお得な物件となる場合があります。
しかし、室内に汚れや異臭が残っていると購入をためらう人も多いため、リフォームをして事故の痕跡を完全になくすことが大切です。事故の影響が一部に留まる場合は、該当部分の壁紙や床を張り替えることで、清潔感のある空間に変えられます。
こちらの記事では、事故物件のリフォームについて解説しています。業者選びのポイントや費用相場も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
特殊清掃をする
リフォームをせずに物件を格安で購入し、自分好みに改装したいと考える買い手もいます。必要以上にリフォームを施すと、かえって敬遠されるケースもあるため、まずは特殊清掃で清潔な状態に整えましょう。
特殊清掃とは、通常のハウスクリーニングでは対応できない汚れや臭いを除去する専門的な清掃のことです。
事故物件の売却では、買い手が心理的抵抗を感じにくい環境を整えることが重要なため、部屋を清潔にすることで購入につながりやすくなります。特殊清掃を行うことで、物件への抵抗感を軽減し、スムーズな売却につなげられるでしょう。
こちらの記事では、事故物件の特殊清掃について解説しています。必要な理由と作業内容も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
期間をおいて売却する
事故物件をすぐに売却しようとすると、買い手の心理的抵抗が強いため、一定の期間をおいてから売却するのも有効な方法です。事故直後はニュースや口コミで情報が広まりやすく、買い手に敬遠される傾向があります。
しかし、時間が経つにつれて関心が薄れ、過去の出来事として扱われやすくなることで心理的ハードルが下がることもあります。
空けるべき期間は、事件の内容や世間の注目度によって異なります。ただし、長期間保有するとコストが高くなる点には注意が必要です。固定資産税や火災保険、管理費や修繕積立金(マンションの場合)などが発生するため、売却のタイミングを慎重に見極めることが大切です。
更地にする
建物を解体して更地にすることで、事故物件としてのイメージを払拭するという方法もあります。建物が残っていると事件を連想させるため、購入をためらう人が多いです。しかし、更地にすることで心理的な抵抗を感じる買い手が減り、購入希望者が増える可能性があります。
また、更地であれば新たな建物を建てやすいというメリットもあります。用途規制や高さ制限などの制約はあるものの、建築の自由度が高く、駐車場や別の用途として活用することも可能です。とくに、立地がよい場所や人気エリアでは売却しやすくなるでしょう。
ただし、更地にしても告知義務は免除されません。建物の解体には数百万円の費用がかかるうえ、更地にすると固定資産税が高くなる点にも注意が必要です。再建築ができないケースもあるため、解体前に専門家へ相談することをおすすめします。
買取専門業者に買い取ってもらう
これまで紹介した方法は、リフォームや解体など、費用がかかる対策が中心でした。費用をかけずにすぐに売却したいという方には、買取専門業者に買い取ってもらう方法もあります。
買取専門業者とは、自ら買主となって不動産を買い取る業者のことです。通常の売却では、不動産会社が仲介して買主を探す必要がありますが、買取業者なら直接買い取ってもらえるため、広告やチラシなどの販促活動は必要ありません。そのため、周囲に知られることなく売却できるのが大きなメリットです。
また、現状のままで売却できるのも利点です。通常の売却では、特殊清掃やリフォーム、不要品の片付けなどに費用と手間がかかりますが、買取業者ならそうした準備なしで売却が可能です。
さらに、短期間での現金化も可能です。一般的な中古物件の売却でも、買い手を探し、契約・引き渡しまでに3〜6か月以上かかることもありますが、買取業者なら事故物件が1〜2週間で売却できます。
「すぐに売却したい」「余計な費用をかけたくない」と考えている方は、買取専門業者の利用を検討してみるとよいでしょう。
まとめ
事故物件の売却価格は、心理的瑕疵が存在するため、一般的な市場価格より下がる傾向があります。孤独死や病死の場合は1〜2割減、自殺は1〜3割減、他殺は3〜5割減となることが一般的です。心理的抵抗の大きい事件ほど買い手が少なくなり、価格が下がります。
スムーズに売却するには、特殊清掃やリフォーム、更地にする、時間をおいて売るなどの方法がありますが、費用がかかり、いつ売れるか分かりません。早く手放したい場合は、買取業者の利用も検討しましょう。
事故物件の売却なら、多摩市の買取業者INTERIQにお任せください。最短即日での買い取りが可能で、特殊清掃やリフォームが必要な事故物件など、買い取りを断られた物件でもそのまま売却できます。
物件買取の知識をもつ専門スタッフがお客さまに親身に寄り添って対応いたします。お見積もりやご相談も無料で承っておりますので、事故物件の売却でお悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせください。


